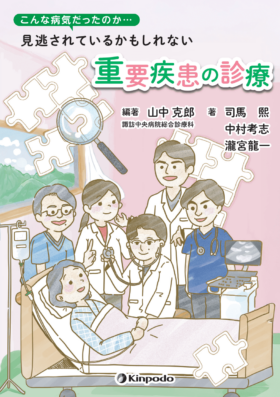最近、当院で流行りの勉強会があります
それは・・・
「國松の内科学を読んでツッコミを入れる会」です 笑
今、巷を賑わせている話題の本ですが、
この本を一番、味わえる読み方をお伝えします
「國松の内科学」は一人で黙々と読んではいけません
一人で読むのは本来の読み方ではなく、
みんなでワイワイ議論したり、ツッコミを入れながら読むのが、
この本の正しい読み方だと思います
映画を見終わった後に感想を言い合う、あの感じに似ています
「國松の内科学を読んでツッコミを入れる会」では
学生さんから初期、専攻医、7〜20年目、院長!?まで年代関係なく参加しており、
30分の間で一つの章をその場で読み、途中でツッコミを入れていきます
例えば、原発性アルドステロン症の章では、
スクリーニングを積極的にやる派とやらない派の意見が繰り広げられたり、
ACTH単独欠損の章では、
ACTHの検査の取り方の記載をして欲しかったという意見がありました
ACTHは室温で保存すると、測定値が低値になることがあり、
意外に知られていないけど重要なので、それを書いて欲しかった・・・
といった感じで、自分がこの章を書くなら、
これは記載する!みたいな感じで自分でさらに作り上げていきます
辞書のように分厚いですが、辞書のように使わずに、
叩き台として使うのが良いかと思います
この本は「國松の内科学」ではなく、
「自分の内科学」にブラッシュアップしていく本だと思います
外来ベースの疾患が多く、
ブラックボックスになりがちな外来診療を知る機会にもなり、
ディスカッションが盛り上がります
「國松の内科学」は内科を10周くらいしたベテランや中堅に特に刺さります
研修医や専攻医には刺さるところもあれば、ピンとこない部分もあると思います
学生さんにとっては、いきなりRPGの攻略本を読むような感じになるかもしれません 笑
初学者の方は教科書も読みつつ、
比べてみると一番勉強になると思います
「國松の内科学」は王道の教科書ではなく、アンチテーゼ的な内容もあり、
教科書には載っていないことも書かれています
(ほとんど参考文献がありません 笑)
あえて議論を巻き起こそうとしか思えない記述もあり、とても議論しやすい本です
國松先生は、この病気をこんな風に捉えているのか〜
と知ることができるだけでも、ありがたいです
読んでいて、笑ってしまうこともあります(特に「上部消化管出血」)
個人的には、毎週、この勉強会が楽しみです
週間ジャンプを読むような待ち遠しさがあります
一人で読んでいるみなさん、
仲間と一緒にツッコミあう会を試してみてはいかがでしょうか?