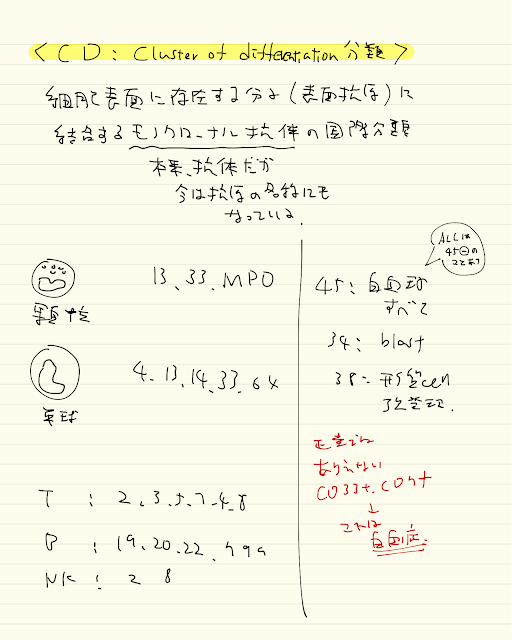身体診察
身体診察の重要性は軽んじられている傾向があります。最近の超音波検査やCT検査、血液検査が診断のkeyとなっていることは間違ありませんが、身体診察の重要性は今後も色あせることなく、輝き続けると思います。身体診察は、病歴聴取よりも大事な局面があります。
するめ まど・みちお
病歴を語ることができない、もしくは上手に自分の物語として語ることができない人たちにとって、身体所見は言葉ではないメッセージであり、それを私達は受け止める力を持たなければなりません。病歴聴取は違います。自発的に答えを言ってくれるような人もいれば、引き出して答えを手に入れないといけない時もあります。どちらかというと、病歴聴取は能動的な力が必要であり、身体診察は受動的な力が必要になります。「攻める問診」に対して、「受け取る診察」ともいえるでしょうか。患者さんは、体全体、もしくは局所の所見で、○○病であると訴えています。それに我々が耳を傾けることができるか、気が付くことができるかが問われています。そのメッセージに気が付いた瞬間、診断が確定することが度々あります。不明熱で原因が分からないと思われていた患者がいたとします。よくみると、鼠径部に黒色の痂疲がついていました。しかし当初はかきむしったものだと軽視され、そのメッセージの重要性を理解できていませんでした。痂疲の意味するメッセージがツツガムシ病でみられるescarであると理解していれば、診断は容易だったはずです。
身体所見を磨くのは、植物を育てるのと一緒
患者は全身で病気を教えてくれます。そのメッセージを受け取る力がなければ、いくら所見があっても診断はつきません。しかし、見る人が見れば、その疾患にしか見えないので、一瞬で診断がついてしまいます。まさに名人芸と呼べる技ですが、これを習得するには、知識と経験が必要です。皮膚筋炎の人の皮膚所見にヘリオトロープ疹やゴットロン徴候があることは知識として知っていても、この皮疹がその徴候であると言い切るのは、経験が必要です。身体所見は一朝一夕に身につくものではなく、じわじわと自分の中に育っていくものであり、植物の芽に水をかけ続けるような作業だと思います。そこに肥料として、上級医からアドバイアスをもらったり、教科書を読んで知識を裏打ちして、根を張っていくことで、自分の身体所見のスキルはどんどん育っていきます。水をかける作業、つまり身体所見を一つ一つ丁寧にとっていく作業を怠って、省略したり、適当にとってしまっては、自分の身体所見のスキルは成長をとめてしまいます。医師として長年経験を積んだとしても、身体所見は上手にとれるようにはなりません。循環器の医師全てが、心雑音を聞き取る能力があるかというとそうとは限りません。身体所見のスキルが必要かどうかは、自分の置かれた環境に依存します。画像検査をすぐにとれない診療所では、特に身体診察の重要度が増します。言葉をうまく話せない小児科も身体所見の重要性は高いです。毎回、画像検査や血液検査ができない環境であると考えて、病歴と身体診察を行うと、切迫感が違うのでスキルアップにつながるかもしれないと思っています。自分のとった所見にこだわりを持つことが重要です。
迅速性
身体所見の特性の一つに迅速性が挙げられます。病歴聴取を行うのはどう考えても数秒から数分は必要です。しかし身体所見はどうでしょう。宝物をよーい、どん、で探すような感じになるので、重要な所見を見つけたら、一発で診断できることもあります。例えば、原因不明のショック、下痢、意識障害の人がいたとして、何を最初に診察しましょうか。体全体にうっすら紅斑があって、充血があったら、それはトキシックショック症候群だとすぐに分かります。手が震えていて、発汗多量で、甲状腺腫大があれば、それは甲状腺クリーゼであると分かります。ミオクローヌスが著明で、腱反射も亢進しており、発汗があり、瞳孔が散大していれば、それはセロトニン症候群であると分かります。同じ文脈でも、身体所見でこれだけの違いがあれば、診断は可能です。もちろん、病歴がとれれば診断にはさらに近づきますが、臨床では自分の目の前に全くの情報がない患者が、今まさに命の火が消えようとしている状態で現れることが稀にあります。病歴聴取や検査も出来ない局面もあるかもしれません。頼れるのは、身体所見だけということもあります。例えば、飛行機の中で出会った意識障害の患者に、あなたは何ができますか。
確実性
病歴は患者が語る情報であり、嘘ではないが、正しくない時が多々あります。何度かきくと、違う内容になったり、一貫性がないことは臨床を長く続けていると分かってきます。しかし、身体所見は違います。収縮期雑音は誰が聞いても、収縮期雑音です。時に、拡張期雑音に変化したりすることはありません。身体所見は動かず、確実にそこに存在しています。確実性をなくしているのは、受け手である医師の責任です。自分の知らないものは見えないし、聞こえないので、時に所見がなかったように扱われることがあります。これは他者のプレゼンやカンファレンスでは特に注意しなければなりません。自分以外の人がとった身体所見を鵜呑みにしてはいけません。これを解決するには、直接、患者さんを診察して、答え合わせをするしか方法はありません。ぜひ、カルテの前でディスカッションするのではなく、実際の患者さんに会って、所見を一緒にとってくれる上級医を探しましょう。口癖が、「じゃあ、一緒に見に行こうか」と言ってくれる上級医はいい上級医です。
5つの目
身体所見をとる上で、3つの目(鳥の目、虫の目、魚の目)で診察を行い、2つの目(機械の目、他人の目)で確認することが重要です。
鳥の目
一つ目は鳥の目です。鳥の目のように空高くから、全体像を伺うことで、自分の置かれた立場、状況がわかり、患者さんの全体像をつかむことができます。自分と患者のおかれた状況が、ショックで具合の悪そうな患者を一人で、救急の部屋で見ようとしている状況だと分かったら、上級医やナースに応援を頼んだり、悠長に病歴をとっている暇がないことくらいわかるでしょう。そして、患者の全体像、つまり見た目やgeneral appearanceをつかむことで、今後の対応が変わります。つらそうにして冷や汗をかいているのであれば、早急に対応が必要であり、不安そうにそわそわしているのであれば、より丁寧に診察を行い、患者の不安を払拭するように心がけ、不安に感じている原因を言及していく必要があるかもしれません。鳥の目でみる身体所見は見た目だけではなく、匂いであったり、声の震え、なんとなくコミュニケーションがうまくとれない感じ、といったような、自分のもつ感覚器を総動員して、その患者から発せられているメッセージを敏感に感じ取らなくてはなくてはなりません。5つの目の中でも最も重要です。
虫の目
2つ目は虫の目であす。鳥の目で全体像をみた後は、虫の目のように局所の所見に注目します。膠原病科医や皮膚科医はまさに代表的な虫の目を使うスペシャリストです。ある時は、爪の生え際の毛細血管をみて、強皮症やSLEを診断することもできるし、ある時は手指のがさがさをみて、皮膚筋炎の診断をつけてしまいます。不明熱患者に手掌や眼瞼結膜の出血班があれば、感染性心内膜炎の診断にぐっと近づきます。適当に手のひらをみても、絶対に気づくような所見ではなく、虫になったつもりで、見に行かないと見落としてしまいます。虫の目で身体所見をとるために重要なのは、必要なのは「局所解剖の知識」です。局所解剖とは、ピンポイントでそこだけの詳しい解剖です。例えば、肩の成り立ちはどうなっているか答えることができるでしょうか。骨と筋肉と関節だけではありません。そこには、腱板とよばれる上腕骨頭を支える構造物があり、関節がスムーズに可動するために、滑液包と呼ばれる構造物があり、筋肉を動かすために支配しているC5の運動神経があります。腱板や滑液包の一つ一つの場所と名前を言うことができ、その障害を発見するためにはどんな身体所見をとればよいか分かるでしょうか。肩だけではなく、体の局所に重要な解剖が存在します。虫の目で診察するには、局所解剖に強くなるということが必要です。つまりはマイナー科と呼ばれる科の解剖に強くなることです。
魚の目
3つ目に魚の目です。魚は水の流れを体で感じ取ることができ、流れを予測することができます。身体所見において、魚の目で身体所見をとることは、身体所見の流動性を意識することです。身体所見は確実だと述べましたが、時間の経過とともに変化していくことは事実としてあります。この流動性を上手に臨床で応用することが、重要です。医師は患者に対して治療を行う、もしくは行わないこともあります。経過観察をするということは、医師にとって実は重要なスキルですが、ただいたずらに時間を過ごすのではありません。診察を行い、身体所見がどう変化するかをみることで、自分の行ったアクションが正しかったのか、間違っていたのかを見極めることができます。感染性心内膜炎の診断はその代表的な疾患です。診断基準に新規の心雑音とありますが、誰がこの心雑音を新規だと言い切ることができるのでしょうか。毎日、心雑音を聴取し、雑音はまだかまだか、と待ち構えているような愚直な医師にしか、この心雑音は新規であると言い切ることはできません。肺炎の治癒過程で、雑音が少しずつ変わることは、毎日、呼吸音を聴取する医師にしか体験できない経験です。この目立たない愚直さこそが、魚の目を持って診察できるているかという事です。
機械の目
右下腹部痛の患者がいるとします。自分のとった身体所見では確実に虫垂炎だと思うので、CTもとらずに、外科医に虫垂炎を手術してくれとは死んでも言えません。絶対、CTとります。色んな理由がありますが、一つは確実ではないからです。身体所見で診断が確定し、治療ができる病気はそれほど多くはありません。間違いのないように検査を行い、確認する作業が必要です。それとともに、身体所見では否定が出来なかった他の鑑別疾患も除外するために検査を行います。CTや超音波が日本ではアクセスが非常によいため、画像検査に走りがちですが、私たちはうまくそれを利用すべきです。例えば、自分は収縮期雑音があると思っており、これはMRだと思ったとしても、それを確認しなければ、あっているのか、間違っているのかわかりません。超音波検査を行ったら、ASであった。あー、この音はASの収縮期雑音なのだ。と間違いに気が付くことができます。自分のとった所見が正しいのかどうかは、毎回feed backを行ったほうがよいです。確認作業を画像で行うか、他の人にお願いするかです。
他人の目
主に上級医、指導医になると思いますが、自分のとった所見が正しいかどうかは、やはり一緒に診察してもらわないと何とも言えません。特に神経領域では顕著だと思います。腱反射亢進や減弱を自信をもって言える研修医がいても、まったく信用しません。上級医は思いもよらない診察をすることがあります。知らない診察法をいっぱい盗むことは研修医の特権ですので、是非、信頼のたる上級医をみつけて一緒に診察してもらいましょう。
これら、5つの目をもって、身体所見をとることが、上達への近道です。
一手間を惜しんではいけない
身体所見をとる上で心がけていることがあります。それは、一手間をおしまないことです。
時間は有限です。診察はなるべく短くして、診断して治療に入りたいものです。そうすると、時間のかかる作業は省略してしまうことがあります。自分の診察より、早く検査や画像をとったほうが、診断につながるのではないか、と考えてしまう時もあります。しかし、身体診察を頑張ってとることでしか、診断につながらないことがあります。検査や画像では代用できないこともあります。例えば、失神の患者の多くは診断がつきません。血液検査や頭部CT、心電図を行って原因がつけられるのは稀です。そんな銃弾爆撃的な検査よりもよっぽど、病歴聴取やシェロングテスト、直腸診の方が診断に役に立ちます。シェロングテストで血圧が低下すれば、それは起立性低血圧を強く示唆しますし、直腸診で血便があれば、失神は大量出血に伴うものであると分かります。ではなぜ、これほど重要な診察がしっかりと順守されていないのでしょうか。それは、忘れていたという理由の他に、手間がかかるのです。思い浮かんでも時間がないから、という理由で行われていないことも多々あります。シェロングテストは右指をクリックすれば、進む検査ではなく、自分で患者に説明をして、数分間患者の様子を観察しないといけないので時間がかかります。しかし、この一手間が診断への近道です。急がば回れです。感染性心内膜炎疑いの患者であれば、少し前かがみにして、ARを聴取しやすくして、ようやく、かすかに聞こえる逆流性雑音を探しにいきます。BPPVであれば、吐き気で苦しむ患者にしっかり説明をして、頭位を変換させてめまいを誘発する手技を行います。寝たきりの患者の発熱に対しては、看護師さんに協力してもらい、背部の観察を行い、褥瘡がないかをチェックします。外来の糖尿病の患者さんは、毎回、靴下をぬいてもらって、怪我してないかを確認します。
このように疾患を診断するためには、「一手間かかる診察」というものが存在します。その一手間を惜しむと、その後、どんな検査を行っても診断がつかないこともありますし、発見が遅れてしまいもっと大変になることがあります。
なので、どんなに時間がなくてもこの診察は絶対行う。一手間かけるぞ。と心に思いながら、診察を行います。
○○眼鏡
身体診察をする時に、鑑別疾患が浮かんで診察をするのと、鑑別診断が浮かばずに診察をするのでは、分けが違います。鑑別診断が浮かんでなければ、まずどこを診察してよいかすら分かりません。咽頭痛があれば、開口障害はないか、口蓋垂の偏位はないか、甲状腺の圧痛はないかといった所見を探します。それは、深頸部膿瘍があって、内側翼突筋にまで炎症が波及すると、開口障害がでることがあり、扁桃周囲膿瘍がひどいと口蓋垂が偏位する人もいるし、咽頭痛といっても亜急性甲状腺炎の人もいるからです。鑑別疾患があるから、その所見をとりにいくのであり、鑑別疾患が思い浮かぶかどうかで、所見が拾えるかどうかが決まります。逆に想起していないものを拾うことは難しいです。例えば、心不全の人が入ってきて、ある人は舌をチェックするでしょう。それは、鑑別診断にアミロイドーシスや甲状腺機能低下症が浮かんでいるからです。鑑別なくして、検査なし。という文言があるが、それは身体所見にも言えることです。そのため、鑑別疾患が思い浮かんだら、「その疾患に見える眼鏡」をかけたつもりで診察するとよいです。必ずこの所見があるはずだと思いながら診察します。めまいの患者さんであれば、BPPVかもしれないが、ワレンベルグが鑑別になります。ワレンベルグを疑ったのであれば、ワレンベルグを拾いにいくような診察をしないと、普通に神経所見をとっていても絶対に見逃します。ワレンベルグを見つけに行く診察は、ホルネル徴候の有無であったり、カーテン徴候であったり、わずかなwide baseであったり、わずかな構音障害です。どれもが、分かりにくいので、見落としがちですが、「ワレンベルグ眼鏡」をかけて診察をすると、ワレンベルグにしか見えてきません。身体診察はそういうものです。見える人には見えるし、見えない人には見えません。
ただ、○○眼鏡をかけることで、pit fallも生まれます。それは、本当に見たいものしか見えていないので、他の所見に気が付かないことです。例えば、複視で困っている人が外来に来ました。当たり前ですが、眼球運動に注目します。そうすると、どうやら左目の下転が障害されているようだ。と分かったとします。ですが、実はその人にはヘリオトロープ疹がありました。鑑別疾患に皮膚筋炎が上がっていなかったので、見落としていました。目は絶対に見ていましたが、全く気が付きませんでした。この人には、実は間質性肺炎があり、呼吸器の先生が後日、指摘してくれました。このように、○○眼鏡をかけて診察する時は、他の所見がとれなくなることを覚えておいてください。
まとめ
・患者さんは例え言葉が話せなくても、
体全体や局所で病気を私達に伝えてくれている(するめ)
・それを我々は身体診察というスキルを用いて、受け止めている(受け取る診察)
・身体診察のスキルを磨くのは、植物を育てるのと一緒であり、時間がかかるし、途中でやめれば、成長は望めない
・実際の診察は鳥の目、虫の目、魚の目の3つの目で診察を行い、機械の目と他人の目で確認を行う(5つの目)
・時に、○○眼鏡をかけて診察を行う
・重要なのは、一手間を惜しまないことである