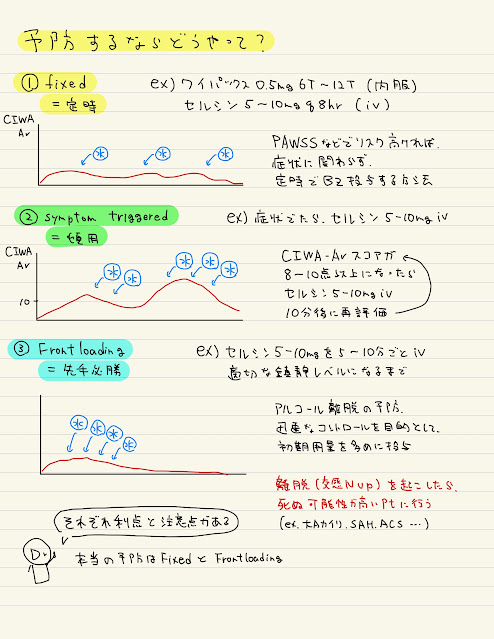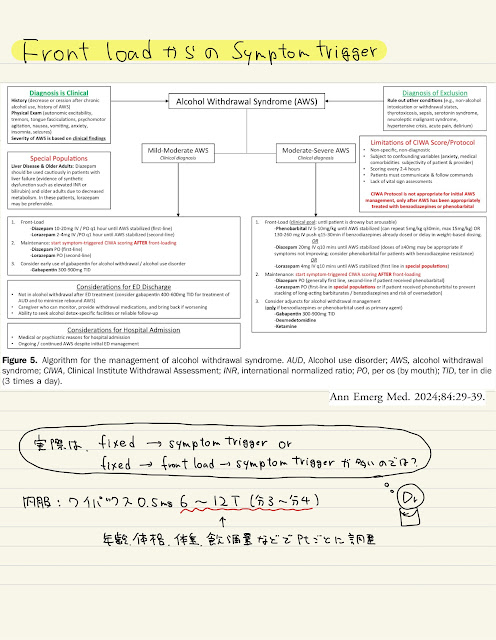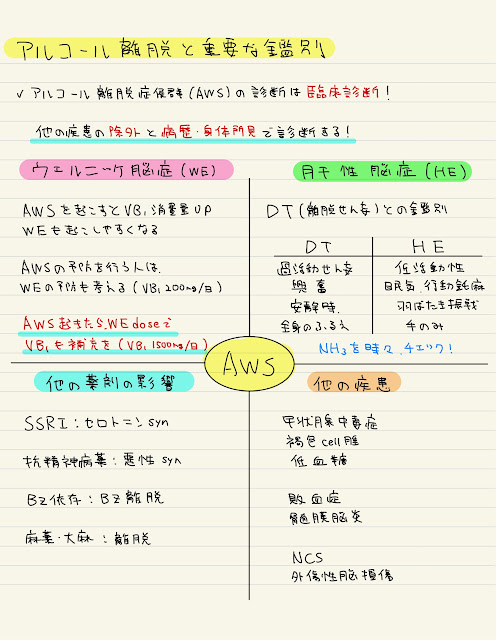専「もともとアロプリノールとか、レバミピドとか、オパルモンとか、
メチコバールとか、ファモチジンとか、
色々入っていますけど、入院中は続けた方がいいんですかね?」
T「そうだね、不要な薬は整理整頓してあげるといいかもね。
外来だとどうしても症状に応じて、対処療法的に薬が足し算されてしまうから、
ポリファーマシーになる傾向があるよね。
患者さんも薬が多くなってきて、何のためにのんでいるか分からないけど、
「一応ください」って、お互い薬のやめ時が分からなくなってしまう。
外来あるあるですね。
自分は、
入院した時よりも、退院する時の方が整っていること
を心がけています。
もちろん、病気によっては難しいこともあるけど、
この意識は大事だと思います。
例えば、
人生の終末期にいる超高齢者に対して本人、家族とACPを行う
ポリファーマシーで薬が余っていた人は、薬を整理する(分3→分1へ)
誤嚥性肺炎を繰り返している人に嚥下リハビリを行い適切な食形態を見極める
さらに退院後もそれを継続できるようなシステムを整える
フレイルでADLが落ちてしまっていた人にリハビリをしっかり行う
外来では分からなかった人となりを入院中にじっくり聞く
実は便秘で困っていたら、便秘に対する薬を調整する
HTやDMにどんな食事がよいか分からない人がいたら、栄養指導を行う
吸入がうまくできていない人がいたら、吸入指導を行う
みたいな感じで、
入院した時よりも退院時の方が、むしろ整っている!
という状態を目指します。
入院した病気をよくすることは当たり前で、
それがしっかりできたら合格点ですが、
せっかくの入院をそれだけで終わらせるのは勿体無いです。
入院は、患者さんにとっては普段接しない医療に濃密に接する時間です。
その時間は実はとても貴重なのです。
ただ、病気を治すだけではなく、
入院してよかったと思ってもらえるように、できることをやりましょう。
小学校の遠足で登山の時に口酸っぱく言われていましたよね。
遠足に行く前よりも、
行った後の方がきれいな山になるように・・・と」
専「え?
言われたことないです。先生のところは田舎だからですかね?」
T「・・・・・。」
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
専「DNARはとったことは何度もありますが、
ACPをちゃんとできる自信がありません。どうしたらいいですか?」
T「そうだね、ACPの本はたくさん出ているけど、
あなたのACPはなぜうまくいかないのか?っていう本知ってる?
専「あー知ってます。途中まで読みました。」
T「この本は今までのACPの本の中で、ずば抜けて素晴らしいです。
自分の実践していたこととも重なりますし、
自分がやってこなかったこともたくさん書かれていて、
ACPはこうやればいいんだ〜ってなる本です。
現時点でのACPの答えみたいな本だね。」
専「そうなんですね、読みます」
T「でもね、教育的にはどうなんだろう・・・っていつも思うんだ。
学びって、答えを知ることじゃないよね?
よく分からないけど、試行錯誤して失敗して、
自分なりに何が失敗の原因か考えて、
違う方法を試して、また失敗して・・・の繰り返しが学びだと思うんだよね。
小学校の夏休みの宿題の問題を解く前に、いきなり答え見たら怒られたでしょ?
答えを見る前に自分で考えなさいって
それと同じような構図なんだよね〜
自分はACPの本なんてない時代から実践して、
ようやく自分なりのやり方に辿り着いた!と思ったら・・・
あの本が出て衝撃を受けました。
同じようなこと言っている先生がいると。
(もちろん中川先生のレベルには遥かに及びませんが)
だから自分はこの本の内容が腹落ちできるまでに15年かかりました。
でも、今の先生達はあっという間に同じレベルに到達できる。
それが学びとしていいのか、よくわかりません。
もっと失敗した方がいいんじゃないかな〜って思う時もある。
ある先生は初めてACPをしたら、
「なんでお前にそんなこと聞かれなきゃいけないんだ!」
ってキレられたことがありました。
そしたら、じゃあ、なんでその患者さんは怒ったんだろうって考える。
その次は同じ過ちは繰り返さなくなる。
そうやって失敗は成長へとつながっていきます。
ACPのいいところは、失敗したとしても生死に関わらないことです。
そして何度でもやり直せる。
何度も失敗しては、振り返り、自分なりの話し方を身につけていくのが、
学びだと思うんだけどね。
その到達点に至ったと思ったら、
あの本を読んで答え合わせするのがいい気もするね。」
H「でも・・・
現時点で最もいいと思われる方法を実践して、
さらに自分なりにいい方法にブラッシュアップすればいいんじゃないですか?」
T「確かにそうだね。
ACPは知識ではなく、技術や態度領域の問題だから、
知っていることと、実践できることには大きな隔たりがある。
あの本の内容は、空手でいう型ですね。球技でいうと綺麗なフォーム。
変な癖を最初からつけると、修正するのが大変だから、
まずはしっかりした型やフォームを叩き込んで、
そこからさらに改良すればいいんだね!
よし、読んでいいよ!」
専「読む本いっぱいあるなぁ・・・」